外国語学習における音読の効用
外国語の学習に音読を取り入れている人は多いと思います。
しかし「そもそも音読とは、何のためのトレーニングなのですか?」と聞かれて、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。
あまりにも当たり前の練習になりすぎてしまい、盲点になっているのかもしれません。
こんなときは専門書に当たってみようと思い、門田修平著「シャドーイングと音読の科学」を読んでみました。この本では音読の効用として下記の2点が挙げられています。
- 単語認知の自動化機能
- 新規学習項目の内在化機能
ちょっと難しいので、以下にひもといていきましょう。
単語認知の自動化機能
私たちは文章を読むとき、実際に声には出さないとしても、頭の中でそれを音声化しています。
例えば、I like coffee. という文を読むとき、「アイ ライク カフィ」という音声を介在して意味を理解しているということです。
音読を繰り返すことで、この音声化が効率的になり、意味理解すなわちリーディングのスピード向上につながるそうです。
新規学習項目の内在化機能
私たちが単語や文法項目を記憶しようとするとき、実際に声には出さないとしても、やはり頭の中でそれを音声化しています。
意味を理解しながら音読を繰り返すことで、この音声化が効率的になり、長期的な記憶の定着に役立つそうです。
音読をしていると、意味がわからないまま読みすすめてしまうこともありますが、それでは記憶の定着につながらないので注意しましょう。
まとめ
ここでは非常に簡略化した形で音読の2つの効用を紹介しました。
本書『シャドーイングと音読の科学』では、非常に詳細な認知のメカニズムが紹介されていますので、興味のある方はぜひ手に取ってみてください。
ただし音読の主目的は「リーディングのスピード向上」「語彙・文法項目の記憶定着」であるとはっきり認識しているだけでも、日々の取り組みが違ってくるのではないかと思います。


 外国語学習法の書籍に関する感想など
外国語学習法の書籍に関する感想など 単語学習に関する二つのポイント − 文脈と類義語
単語学習に関する二つのポイント − 文脈と類義語 『外国語上達法』読書ノート⑪ − レアリア
『外国語上達法』読書ノート⑪ − レアリア 『外国語上達法』読書ノート⑤ − 文法
『外国語上達法』読書ノート⑤ − 文法 『外国語上達法』読書ノート − はじめに
『外国語上達法』読書ノート − はじめに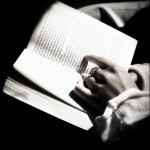 英文速読の技術 − スキミングとスキャニング
英文速読の技術 − スキミングとスキャニング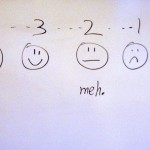 語学力の5段階評価 − ロンブ・カトー著『わたしの外国語学習法』より
語学力の5段階評価 − ロンブ・カトー著『わたしの外国語学習法』より Finnish as a third language − 第三言語としてのフィンランド語習得を考える
Finnish as a third language − 第三言語としてのフィンランド語習得を考える
3月 07, 2013 @ 09:18:40
Huomenta!
いつも楽しみに読んでます。
今回はとても良いことを解説していただき,勉強になりました。
Kiitos paljon!
3月 13, 2013 @ 17:49:52
Jussiさん
コメントありがとうございます。
最近は基本に戻って教科書(Suomea Suomeksi)の音読をしています。
なかなかすらすら読めるようにはならないのですが、日々練習ですね。