フィンランド語学習記 vol.171 − 命令文の目的語

最近のエントリーで、フィンランド語の命令文について扱いました。
フィンランド語学習記 vol.169 − 命令文(二人称単数) | Fragments
フィンランド語学習記 vol.170 − 命令文(二人称複数) | Fragments
命令文を作る際に注意しなければならないのは、実は動詞の形だけではないようです。
先日のフィンランド語教室ではこんな例文も扱いました。
1)Voitko avata oven?(戸を開けてくれませんか。)
2)Avaa ovi!(戸を開けなさい。)
3)Älä avaa ovea!(戸を開けるな。)
*avata(開ける)、ovi(戸)
2)Avaa ovi!(戸を開けなさい。)
3)Älä avaa ovea!(戸を開けるな。)
*avata(開ける)、ovi(戸)
1は疑問文、2と3は命令文ですね。
動詞 avata の変化はさておき、注目してほしいのが目的語 ovi の形。何と1〜3の全てが異なっています。
1→[対格]oven
2→[主格]ovi
3→[分格]ovea
2→[主格]ovi
3→[分格]ovea
何でこうなるかなあーという感じですが、落ち着いてルールを検証していきましょう。
一つ・二つと数えられる目的語の全体を表すときは対格
1)Voitko avata oven?(戸を開けてくれませんか。)
「戸」というのは一枚・二枚と数えることができます。
また戸を開けてほしいということは、戸全体を開けることにつながるので、ここでは全体を表す対格を用います。
命令文の目的語は主格
2)Avaa ovi!(戸を開けなさい。)
これについて、ロジカルな説明をひねり出そうとしてみたものの、どうにも思い付かず。
とにかく命令文の目的語は主格!と覚えておくほかなさそうです。
否定文の目的語は分格
3)Älä avaa ovea!(戸を開けるな。)
戸を開けないでほしいということは、(あたりまえですが)戸全体を開けることにはつながらないので、ここでは全体を表す対格ではなく、部分を表す分格を用います。
これらの用法はなかなか複雑。
相手の言うことを理解するだけならともかく、自分が話すときにきちんと使い分けるのはかなり高いハードルだと思います。
それでもコツコツと練習していきましょう(涙)。
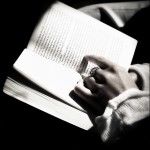 フィンランド語学習記 vol.112 − 目的語の格変化
フィンランド語学習記 vol.112 − 目的語の格変化
3月 23, 2014 @ 19:18:32
命令文の目的語は主格と覚えるより、命令文では対格の目的語は使えないと覚えておいた方が良いような気がします。と、いうのは
Puhu suomea! のようにもともと分格を目的語にとる動詞は命令文になっても目的語は分格のままだからです。
また、すでに習ったかもしれませんが Minun täytyy… のような義務を表す文の場合もtäytyyに続く動詞の目的語は対格は使えませんが、分格はそのまま使えます。
おっしゃていたように、フィンランド語で書かれた文を読む場合は、さほど意識しなくてもいいのですが、いざ自分で話したり書いたりするときになると目的語の格を使い分けるというのはなかなか難しいです。
ですが、たとえばフィンランドに旅行した場合、目的語の格を気にするよりとにかくフィンランド語で話してみることのほうがたいせつだと思いました。
3月 24, 2014 @ 19:27:38
juokseva nipsuさん
コメントありがとうございます。なるほど、命令文でも分格はそのまま使えるんですね。とすると、目的語が数えられない名詞(分けられる名詞)の場合はやや楽ということになりますね。朗報です!
おっしゃるとおり、実際にカタコトでフィンランド語を話すことになったら、格など意識せずにひたすら単語を並べることになるんだろうなあと思います。
それで通じればまだよいのですが、実際はどうなるやら。。。でも早く旅行などで試してみたいですね。