「英語がペラペラになりたい」と思っている人へ − 外国語ペラペラの科学

photo credit: Baby and Friend via photopin (license)
中学・高校と人並みに英語を勉強してきました。大学は英文科。海外留学も経験しました。
よってそれなりに英語での会話はできるものの、とても流暢とはいいがたい。
「ああ、英語がペラペラになりたいなあ」と思ったことはありませんか? 。。。はい、これ自分のことですが。
現代の英語学習においては、いわゆる「グロービッシュ」という言葉に代表されるように、流暢でなくても意思の疎通ができればよい、という意見が主流になっているように思います。
私個人はこの考えにどちらかと言えば賛成なのですが、そうは言っても「あるべき姿」と「ありたい姿」は違う訳で、英語が流暢な人を見れば素晴らしいと思わずにはいられません。
甲子園を目指して練習に打ち込んでいる高校球児に「野球なんかそんなに上手くならなくていいんだよ。バッティングセンターで100キロくらいのボールを打ち返せればオーケー。あまりハードな運動は健康を害するから、中止中止。」と言ったところで、ボールを投げつけられるのがオチでしょう。
そのように人間の向上心というのはとどまることを知らず、練習に熱が入るのも無理のないこと。
。。。
さて英語の話に戻りましょう。「英語がペラペラになりたいなあ」と思うこと自体は良いとしても、そもそもペラペラというのはどのような状態のことを指すのでしょうか?
すぐに思い付くのは、
- よどみないリズム
- きれいな発音
といったあたりでしょう。しかしこれだけではよくわかりません。
幸い第二言語習得理論の中に流暢さ(fluency)についての研究があるので、今回のエントリーではそのいくつかを取り上げてみたいと思います。
外国語がペラペラであるとはどのような状態を指すのか?
まず、Guillot(1999)は外国語学習における fluency を4つの観点で定義しています。
1)The ability to produce written and/or spoken language with ease
話し言葉・書き言葉をたやすく産出する力
2)The ability to speak with a good but not necessarily perfect command of intonation, vocabulary, and grammar
必ずしも完全ではないかもしれないが、よいイントネーション・語彙・文法で話す力
3)The ability to communicate ideas effectively
考えを効果的に伝える力
4)The ability to produce continuous speech without causing comprehension difficulties or a breakdown of communication
理解不足に陥ったり、コミュニケーションが中断したりすることなく、よどみなく話すことができる力
おおむね納得できる定義でしょうか? しかしよく考えてみると、これらの力というのは必ずしも第二言語に特有のものではありません。
例えば、3の「考えを効果的に伝える力」というのは母語でも個人間の格差があるものだと思います。本稿で問題にしたいのは「母語」ではなく「第二言語」における fluency な訳ですが、そもそも第二言語に特有の、つまり母語では問題がないのに第二言語になったとたんにつまずいてしまうポイントとは何でしょうか。
De Bot(1992)によると、それは「語彙・文法・発音」であるということになるのですが、それでは当たり前過ぎるので少し視点を変えてみましょう。
ここに二人の英語学習者がいるとします。一人は1年前の自分です。もう一人は1年に及ぶ語学留学から帰国したばかりの今の自分です。
この二人のうち、英語が流暢なのはどちらですか?と聞かれたら、あなたは自信を持って今の自分と答えることでしょう。
しかし、どうやったらそれを証明することができるのでしょうか?
ひとつ考えられるのは TOEIC や TOEFL などのスピーキングテストを受けることかもしれません。それは確かに一つの指標となり得ます。
しかし厳密に言えば、それは語彙力や文法力を含む英語の総合的な能力を、スピーキングというフィルターを通して見ているに過ぎません。また厳密な採点基準があるとしても、採点のプロセスにおいて採点者の主観を排除することはできません。
外国語がどのくらいペラペラであるかを測定することはできるのか?
本稿で問題にしたいのは、英語の知識ではなく純粋な「流暢さ」そのものです。それはそもそも客観的に測定できるような性質のものなのでしょうか?
実は、第二言語習得に関する研究の中では、そのような試みに挑戦したものもあるのです。
例えば、Lennon(1990)の研究では、イギリスの大学に半年間留学したドイツ人大学生4名を対象に、留学前と留学後にスピーキングテストを行い、その変化を測定しました。テストでの調査項目は多岐に渡りますが、例えばスピーキングの一定量に含まれる、
- 単語数
- 「あー」「えー」などのつなぎ言葉の割合
を調べたところ、留学当初から留学終盤にかけて「単語数は増え、つなぎ言葉は減る」という結果が見られたようです。
ただこのような測定方法には限界もあり、例えば発音の善し悪しなどは客観的に評価するのが難しい項目の一つです。
また単に単語数が多いということや、つなぎ言葉の割合が少ないということが、本当に流暢さの指標に成りうるのか議論の余地はあることでしょう。決して「早口=流暢さ」ではありませんので。
またテストの時のように集中して脳を絞るのではなく、リラックスした状態でも同じように話せるというのでなければ、真の意味でペラペラとは言えないでしょう。しかしもちろん脳の中を直接観察することはできません。そこにはやはりブラックボックスがあるのです。
そこで、Segalowitz(2010)は「流暢さ」をより詳細に3つのカテゴリーに分けて論じています。
a) cognitive fluency(認知的な流暢さ)
- the efficiency of operation of the underlying processes responsible for the production of utterances
b) utterance fluency(発話の流暢さ)
- the features of utterances that reflect the speaker’s cognitive fluency
c) perceived fluency(知覚された流暢さ)
- the inferences listeners make about speakers’ cognitive fluency based on their perceptions of their utterance fluency
わかりやすく言えば、a は「脳内の処理能力」、b は「発話そのもの」、c は「我々が受ける印象」ということになるでしょう。
客観的に測定できる指標は b だけですが、それを氷山の一角とすると、海に沈んで見えない a の部分があるということ。
また私たちが感じる「あの人はペラペラだなあ」という印象は b に基づいて a を類推した c であるということ。
こうして見ると、かなり問題が整理されたように感じます。
それではいったいどうすれば外国語がペラペラになれるのか?
ここまで流暢さについて長々と述べてきましたが、結局一番気になるのは次の質問でしょう。
この質問に対する答えはシンプルです。
拍子抜けしてしまった人がいたら申し訳ありません。。。補足すると、アウトプットとインプットを繰り返すことによって、さきほどの a の「脳内の処理能力」を鍛えることができる、そのことによって b の「発話そのもの」を流暢にすることができるということになります。
ただ本稿を読んでくれている人の中には、読み書きは得意だけれど、会話は苦手。。。という人も多いのではないでしょうか。
自分は性格が内向きだからペラペラにはなれないだろうなあ、と感じている人もいるかもしれません。
実はパーソナリティや心配性と外国語の流暢さの関係を調べた研究もあるのです。
Oya et al.(2004)の研究では、ニュージーランドの語学学校で学ぶ日本人学生73名に「性格診断・心配性調査」を受けてもらい、その上で英語のスピーキングテストを行いました。
その結果、外向的な人は採点者の印象が良くなる傾向があるけれども、発話の量や沈黙の長さといった客観的な指標で比較した場合、「内向的な人と外向的な人」「心配性の人と楽観的な人」の間で統計的に有意な差は見られなかったそうです。
従ってどんな人も「練習」を積み重ねることによって、ペラペラへの階段を一歩ずつ登ることができる。このことはあらゆる外国語学習者への力強いエールになるのではないでしょうか。
- De Bot, K. (1992). A bilingual production model: Levelt’s “Speaking” model adapted. Applied Linguistics, 13, 1-24.
- Guillot, M. (1999). Fluency and its teaching. Clevedon: Multilingual Matters.
- Lennon, P. (1990). Investigating fluency in EFL: A quantitative approach. Language Learning, 40(3), 387-417.
- Oya, T., Manalo, E., & Greenwood, J. (2004). The influence of personality and anxiety on the oral performance of Japanese speakers of English. Applied Cognitive Psychology, 18, 841-855.
- Segalowitz, N. (2010). Cognitive bases of second language fluency. New York: Routledge
 外国語学習法の書籍に関する感想など
外国語学習法の書籍に関する感想など 単語学習に関する二つのポイント − 文脈と類義語
単語学習に関する二つのポイント − 文脈と類義語 『外国語上達法』読書ノート⑧ − 辞書
『外国語上達法』読書ノート⑧ − 辞書 『外国語上達法』読書ノート⑤ − 文法
『外国語上達法』読書ノート⑤ − 文法 『外国語上達法』読書ノート④ − 語彙
『外国語上達法』読書ノート④ − 語彙 外国語の勉強をするのに適した場所は?
外国語の勉強をするのに適した場所は?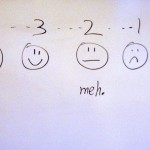 語学力の5段階評価 − ロンブ・カトー著『わたしの外国語学習法』より
語学力の5段階評価 − ロンブ・カトー著『わたしの外国語学習法』より Finnish as a third language − 第三言語としてのフィンランド語習得を考える
Finnish as a third language − 第三言語としてのフィンランド語習得を考える


 文法上の「複数形」の必要性について
文法上の「複数形」の必要性について UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger − 日本国内の危機言語とは?
UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger − 日本国内の危機言語とは?
 big と large の違いとは?
big と large の違いとは? Aussie joke about Australian rules football
Aussie joke about Australian rules football tomato の複数形は「tomatoes」なのに、piano の複数形が「pianos」になるのはなぜか?
tomato の複数形は「tomatoes」なのに、piano の複数形が「pianos」になるのはなぜか? 『ツカウエイゴ』の電子書籍を読んでみる
『ツカウエイゴ』の電子書籍を読んでみる 最先端の英単語を紹介するウェブサイト『Word Spy』
最先端の英単語を紹介するウェブサイト『Word Spy』 Euouae
Euouae Google 翻訳の今と未来 − from Google I/O 2013
Google 翻訳の今と未来 − from Google I/O 2013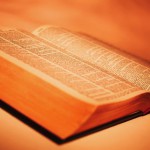 ある英語辞書において最もよく調べられた単語とは?
ある英語辞書において最もよく調べられた単語とは? よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 新語はどこからやって来るのか? − Case of ‘QUIZ’
新語はどこからやって来るのか? − Case of ‘QUIZ’


 表現力が身に付く「連語辞書」のすすめ
表現力が身に付く「連語辞書」のすすめ どうしようもなく疲れたときの英語表現
どうしようもなく疲れたときの英語表現 See you later, alligator.
See you later, alligator. わたしとあなたの境界線
わたしとあなたの境界線 宮川幸久編著/山岸和夫・西世古柳平著『中学英語Q&A実用指導事典』
宮川幸久編著/山岸和夫・西世古柳平著『中学英語Q&A実用指導事典』 Xで始まる英単語
Xで始まる英単語 英会話における filler(つなぎ言葉)について
英会話における filler(つなぎ言葉)について 英文メールの結びには何を使う? − complimentary close in email
英文メールの結びには何を使う? − complimentary close in email Secessionist − from Wordnik Blog
Secessionist − from Wordnik Blog the signs of the zodiac − 十二星座の英語たち
the signs of the zodiac − 十二星座の英語たち